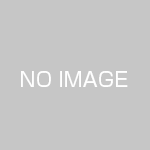妖怪手品
妖怪手品
江戸時代の人々の妖怪観がよくあらわれた「妖怪娯楽」として、まずは「妖怪手品」がある。
「妖怪手品」とは、妖怪や妖怪がひき起こすとされた現象を出現させる手品のことである。
手品はかつて「幻術」と呼ばれ、妖術のたぐいと区別のつかないものであった。
ところが江戸時代中期、18世紀に入る頃になり、手品の種明しをする本が続々と出版され、手品は誰にでも再現可能な「遊び」に変わっていった。
そうした本に紹介された手品のなかに、「妖怪手品」をしばしば見出すことができる。
なかでも宝暦14年(1764)に大阪で刊行された『放下筌(ホウカセン)』は、自ら「化物の本」であることをうたい、多くの「妖怪手品を」紹介している。
幻灯器
幻灯器は17世紀にヨーロッパで発明され、日本にはオランダから長崎貿易を通じてもたらされたが、18世紀後半にはすでに商品化されて眼鏡屋などで売られていたことが、『天狗通』の記述からもわかる。
幻灯器はラテン語でランテルナ・マギカ、つまり「魔法のランタン」と呼ばれ、オランダ語ではトーフェル・ランタールン、「悪魔のランタン」とよばれていたことからわかるように、はじめから何やら怪しいものを生み出す道具としてイメージされていた。
日本でも、幻灯器は「妖燈」「招魂燈」などと訳され、まさに妖怪や幽霊を出現させる道具ととらえられていたのである。
写し絵・妖怪狂言・怪談噺
「妖怪手品」はいわば素人の座敷芸としておこなわれたものであったが、19世紀にはいると、仕掛けを用いて妖怪・幽霊を出現させることがお金を取って見せる芸能へと発展する。
まずは享和3年(1803)に都屋都楽(みやこやとらく)によって創始された「写し絵」がその一つである。
西洋から伝えられた幻灯が、18世紀後半にはすでに商品化されたいた。
これが日本風にアレンジされ、芸能として確立されたのが写し絵である。
都楽はもともと焼き物などに彩色を施す上絵師だったが、上野山下でおこなわれた「エキマン鏡」とよばれる幻灯の興行を見て自分でも同じものが作れないかと思い立ち、蘭方医を父に持つ友人の協力を得て、ガラスに絵を描く薬法を発明した。
そして、それを用いて自分で種板を描き、幻灯の興行を始めたのである。
明和2年 江戸両国で「雷獣」の見世物
江戸時代には、さまざまな珍しい物や動物、人間などが見世物にされたが、そのなかには妖怪といえるものも少なからず混じっていた。
例えば明和2年(1765)には、江戸両国で「雷獣」の見世物があった。雷獣とは、落雷とともに天から落ちてくるとされた伝説上の獣である。
この見世物にされたのはイタチのような黒い獣で、特に変わった姿をしていたわけではなかったが、言い伝えでしかしられていなかった獣の実物がみられるということで、多くの見物客があつまったのことである。
安永7年(1778)、両国回向院での信濃善光寺阿弥陀如来の出開帳にあわせておこなわれた「鬼娘」の見世物は、当時たいへん話題になり、「鬼娘」を題材にした草双紙がいくつも刊行され、一種の社会現象にまでなった。
鬼娘は、頭に袋角(ふくろづめ)という瘤のような隆起があり、鬼のような風貌をした女性で、それが舞台の上で、かぶっていた打掛をとり素顔をさらすというだけの見世物であつたが、たいへんな評判をとり、おびただしい数の群衆が詰めかけた。
その人気の裏には、やはり伝説や昔話でしか知らない鬼の実物を目にしたいという人々の欲求が働いていたようにおもわれる。
この鬼娘の見世物には、皮肉な末路が待っていた。
鬼娘の人気に目をつけた別の香具師の手によって、鬼娘の偽物が登場したのである。
それはなめし革で顔を作り、蠟石の牙と子牛の角をつけたまったくの作り物だったのだが、そちらのほうが絵に描かれた鬼に似ていたので、やがて本物を圧倒してしまったという。
「作られた妖怪」のほうがより妖怪らしいとみなされたというのは、「フィクションとしての妖怪」がめざましい発達を遂げた江戸時代らしい出来事だったといえるだろう。
まさに、見世物の妖怪とは「作られる」ものであった。