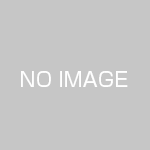野暮と化物は箱根から先
妖怪に対する新たな態度
中世までの妖怪とは、人間にとつてたびたびひたすらに恐怖の対象、畏怖の対象であった。
ところが江戸時代なると、それとはまったく異なる態度がみられるようになる。妖怪を娯楽として楽しむという態度である。
もっとも、娯楽の題材となったのは、人工的に再現され、表象化された妖怪・・・わかりやすく言えば、フィクションとしての妖怪であった。
江戸時代は、このようなフィクションとしての妖怪というものが独自の発達を遂げ、人々の遊びや楽しみに貢献するようになった時代であった。
そして、これは妖怪のリアリティの喪失と表裏一体をなす現象であった。
江戸時代中期の十八世紀後半ごろからしばしば用いられるようになったことわざに、「野暮と化物は箱根から先」「ないのは金と化物」「下戸と化物は世の中になし」などとというものがある。
化物、つまり妖怪「ないもの」の代名詞だったのである。
妖怪信仰のゆらぎ ~江戸時代~
江戸時代の妖怪は、「ないもの」の代名詞だった。
その根底には、日本人の自然観、神霊観の変容があったと考えられる。
中世までの日本人の世界認識のなかでは、自然は人間より上位にあり、その具現化である神霊や妖怪は、畏れと恐怖の対象であった。
ところが江戸時代になると、自然の恩恵とも脅威とも無縁な生活を送る都市の住民のあいだで、そうした畏怖の念はしだいに減退していった。
また貨幣経済の発達が、「お金の力で何でもできる」というような考え方を生み出し、神仏との関係も貨幣(お賽銭)を介した対等の立場へと変わっていった。
こうして自然や神霊に対する畏怖の念が薄らいでいった結果、それらと不可分に結びついていた「妖怪信仰」そのものが揺らいでいった。
さまざまな怪異や妖怪は、心の迷いや目の錯覚、あるいは単なる「物理的」「生物学的」な現象、狐や田向のしわざ(狐や狸が人を化かすということは、江戸時代の人々にとってまだ「生物学的」な現象であった)などとして脱神秘化されていったのである。