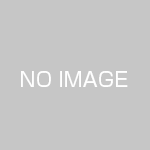草双紙の「化物」たち
草双紙の「化物」たち
「キャラクター」としての妖怪」の源泉となったのは、妖怪を題材にした絵本であった。
妖怪を題材にした絵本は、比較的早い時期にあらわれていた。
昭和55年(1980)、三重県松坂市射和(いざわ)町の旧射和寺大日堂に安置されていた木造地蔵菩薩坐像の坐像の胎内から10冊の絵本が発見され、寛文期(1661~73)に上方で刊行されたものと推定されたが、これが現存最古の子供絵本といわれている。
実はこのなかに、妖怪を題材にした絵本がすでに見られるのである。
そのうちの一つ、『天狗そろへ』は、「筑紫彦山の豊前坊」にはじまる日本全国の天狗を1つ1つ紹介したもので、「妖怪図鑑」的な絵本の先駆けとみなすことができる。
享保(1716~36)以降は、江戸では草双紙とよばれる形式の大衆的な絵本が大量に出版されるようになる。
それらは表紙の色から赤本・黒本・青本・黄表紙などと類別されているが、そのなかでは妖怪はすでに古臭いもの、時代おくれのものとして扱われ、怖ろしさや神秘性を失っていた。
むしろそれらは、さまざまな特性を持った「キャラクター」として登場し、読者の目を楽しませていたのである。
こうした草双紙に登場するようなキャラクター化された妖怪を、江戸時代の人びとは「化物」と呼んでいた。
草双紙のなかの妖怪「化物」
『化物見世開』(ばけものみせびらき) 寛政12年(1800)に刊行された十返舎一九(じゅっぺんしゃいっく)作画にえかかかれている、もはや恐ろしい存在ではなく、世俗にまみれた滑稽な存在としての妖怪たちである。
このように、草双紙のなかの妖怪-「化物」たちは、恐怖ではなく笑いをもたらすものだった。
そこには、江戸時代の人間中心主義的な世界観が反映されている。
江戸時代の(とりわけ都市の)人々にとって、自然とその象徴的存在てある妖怪はもはや畏怖の対象ではなく、人間よりも下位にある存在だったのである。
こうした草双紙の「化物」たちは、それぞれ明快な性格づけがなされ、その「お約束」のなかで行動していた。
例えば、「見越入道」は首の長い入道姿の化物とされ、さらに化物たちの親玉という性格づけがされていた。
「豆腐小僧」は手に豆腐をのせた盆をもってあらわれ、狸は陰〇を八畳もの大きさにひろげることができ、幽霊は白い着物を着た足のない美女の姿で描かれる。
これらは実際の民間伝承にねざした妖怪でありながら、独自の性格づけがなされたものになっている。