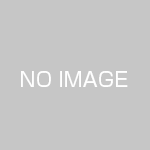長州藩と四国艦隊との戦い
長州藩と四国艦隊との戦い
攘夷に凝り固まっていた長州藩は、「五月十日を期して攘夷を実行する」という幕府の奉答を、そのまま実現
しようとした。つまり、1864(元治元)年5月10日、下関海峡を通ろうとしていたフランス・オランダの軍艦に
砲撃を加え、これに損害を与えたのである。
このあと長州藩は、亜米利加・フランスのわずか三隻の軍艦によって、さんざんな目にあわされている。けれ
ども、一向にこりない。かえって九州・小倉の武備を固め、下関海峡をはさむ下関と小倉の両方で、ここを通る
船を関しするようにした。また、敵の襲来にそなえて、城下町・萩の沿岸に土塁を築いた。その土塁をつくると
きには、武士はもちろんのこと、農民や町人・僧をはじめ、女・子供までが集まって手伝いをしたという。
また「農民・町人であっても、刀を持ち、武芸をならってもよい」と許したりもしている。このように農民や
町人にも武器を持たせ武芸をならわせることは、そのころの他の藩では考えられもしないことであった。
そまり長州藩では、藩をあげて外敵をふせぐためのそなえを固めようとしたのである。
そのような中で、高杉晋作を中心に奇兵隊がつくられたことも忘れることはできない。これは、武士・農民・
町人という身分に関係なく、体が丈夫で、国を守ろうとする熱意をもつ者はたれでもはいれるという新しい姿の
軍隊であった。そして、奇兵隊の結成をきっかけに、ほかにも遊撃隊・八幡隊など多くの隊がつくられた。
このような長州藩の姿は、日本条約を結んだ各国にとってたいへん目ざわりであった。そして、「このままにしておいたら、日本人はつけあがり、外国人をるようになばかりだ。いまこそ彼らが懸命になって整備している軍備が、文明諸国の力の前ではまったく無力であること、外国を敵とすることがいかに危険であるかということを存分に知らせる必要がある。」という意見をまとめるようになった。
その結果、四国艦隊による長州攻撃となった。それは8月5日のことである。この少し前の7月、長州藩は禁門の戦いで敗退している。また、第一次長州征伐の命がくだされていたときでもあった。ところで、四国艦隊との戦いも長州藩の惨敗におわった。文明の違いは、あまりに大きかったのである。そのことは次のような戦いの記録からもよくわかる。
「イギリス船からの発砲は、たばこ1.2服吸う間に数百というくらい、はげしいものであった。浜の台場などは、敵の砲弾で砂がとばされるので、20間(36m余り)もうしろにいないと、砂で目も口もあけていられないほどであった。もちろん味方の砲台からも攻撃すのだが、いくら発砲しても敵の船には鉄製で丈夫だから、すこしもこたえない。そこで砲台の者たちは、砲戦では勝味がないと陣屋を焼いて退却した。その様子を敵はマストの上から遠眼鏡(望遠鏡)で見定め、ただちに上陸してきた」
こうして上陸した水夫はたちは、砲台に備えてあった大砲をこわしたり持ち帰ったりした。すでに火薬庫はすべて焼き払われている。砲弾もた海に投げこまれ、長州藩が藩をあげて装備してきたものは、わずかに2日の戦いで、そのほとんどをうしなってしまうことになつたのである。
やがて戦いの後始末のための講和談判が行われたが、この敗戦は、長州藩の考え方を大きく変えるきっかけとなつた。つまり、「攘夷はむだである」「いくら攘夷をししようとしても、それは実現できない。むしろ進んで外国と交わるようにすることの方が大切なのではないか」という意見がつよまることになったのである。
四国艦隊
艦船17隻、兵員5千人余り、砲288門という四カ国連合軍の結成を主導したのは、イギリス公使オールコックであった。彼は、幕府による事実上の横浜鎖港と長州判による下関海峡封鎖とが、通商関係阻害の重要な要因であると考え、この挙にでたのである。
彼の思惑どおり、連合軍による攻撃は、その後の国内政局・外交の重要な転機になった。薩長がイギリスとの接近を深めたのも、この事件がきっかけになっている。
長州藩が結んだ講和条約
四国艦隊に惨敗した長州藩は、高杉晋作を代表として、講和のための条約を結んだ。その高杉のもとで活躍した
のが、密航してイギリス留学を試み、事件に驚いて急遽帰国した井上聞多(馨)・伊藤俊輔(博文)である。
このとき結ばれた条約の内容は、次のようであった。
・外国船が馬関(下関)を通るときには、親切に取り扱う
・船中で必要な、石炭・食料・薪水などを売り渡す
・難波しそうになったときには、上陸を許す
・新しく台場を築いたり、大砲を備えたりしない
・下関を焼き払わない代わりに、償金を出す
このうち償金は、「長州による砲撃は、幕府の命を受けたものなので、幕府に責任がある」ということになり、幕府が支払うことになった。