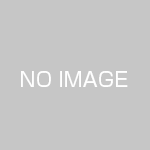阿倍仲麻呂と吉備真備
阿倍仲麻呂と吉備真備
≪唐で学んだ人≫を考えるとき、阿倍仲麻呂と吉備真備の名を忘れることはできない。
この二人は、ともに717年出発の遣唐使に、留学生としてついていったのであるが、その一生は、まったく違った道を歩むことになつた。仲麻呂は20歳で唐に渡り、都の長安京で儒学・法律・文学・数学、そのほかさまざまな学問を学んだ。そして、いずれについてもすぐれた成績をおさめたのち、科挙の試験を受けた。これは役人になる者を選ぶためのもので、唐の国の人でもなかなか合格できない、むずかしい試験である。しかし、仲麻呂はこの試験にも合格し、唐の朝廷につかえる役人になった。
玄宗皇帝にもみとめられた仲麻呂は、次々と高い位にのぼるとともに、皇帝の皇子の学友ともなるほどであった。
また、中国第一の大詩人といわれた李白とも親しく交わるなど、その名は、唐の朝廷内に、広く知られるようになった。また、日本からの留学生や学問僧で、仲麻呂の世話になった者は、数知れないほどであったという。こうしているうちに、早くも35年の年月がたってしまった。
いまはもう、朝廷の中でおしもおされもしない地位を築きあげた仲麻呂も、故郷の日本がなつかしくてしかたがなくなっていた。実は、その20年ほど前に遣唐使がきたときも、「ぜひ帰国したい」という願いを、玄宗皇帝に申し出たのだのである。しかし、このときは、仲麻呂の才能を惜しんだ皇帝が、帰国を許してくれなかった。
ところが、752年、また遣唐使がついた。「今度こそ帰りたい。今帰らなければ、もう日本に帰る機会はこないだろう」仲麻呂の願いは、今度は許されたが、しかし仲麻呂は、日本の土を踏むことができなかった。仲麻呂を乗せた船は南へ南へと流され、ベトナムについてしまった。そればかりか、同じ船に乗っていたものは、賊に襲われて殺されたり、病気で死んだりした。そして、仲麻呂ら十数人が、ようやの思いで長安までたどりつくありさまだったのである。「仲麻呂は死んだ」とばかり考えていた長安の人々は、仲麻呂らを涙とともに迎えた。その中には、『晃卿を哭す』(仲麻呂の死を悲しむ)という詩までつくった大詩人李白もいた。その後、仲麻呂が日本へ帰る機会はなく、彼は長安京でその一生を終えた。
しかし、帰国の旅に出るとき、その送別の宴で彼がよんだ次の歌は、私たちに、日本をなつかしんだ仲麻呂の心を、いまも伝えてくれる。
天の原 ふりさけみれば 春日なる
三笠の山に 出でし月かも
(大空を見渡すと、今、月が昇ってくる。ああ、あの月は故郷の奈良の三笠山に出た月と同じ月だ。故郷の人々も、この月をながめているのだろうか)この仲麻呂に対して、吉備真備はは、23歳で唐につき、儒学・天文学・暦学・軍事学などを学んだあと、735年に日本に帰ってきた。約18年の間、唐で勉強したことになる。
帰国した真備は、さっそく朝廷につかえ、重要な役につくようになった。このころ、朝廷では、右大臣の橘諸兄(たちばなのもろえ)が勢いをふるっていた。真備は、玄ぼうという僧とともにこの諸兄に認められ、その片腕となって働くようになったのである。長い間、唐で学んでこの二人の知識には、朝廷の役人たちもといていかなわなかったらしい。そのため、ねたまれたり憎まれたりしたことも多かったという。真備は、遣唐副使としても唐に渡った。実は、阿倍仲麻呂が帰国しようとしたときには、真備もいたのである。
しかし、仲麻呂とは別の船に乗っていた真備はは、無事日本に帰りつくことができた。真備には、幸運の星がついてまわったのであろうか。帰国後の真備は、さらに右大臣の位にまでのぼって、政治の上で重要な役割を果たしたのであった。
このように仲麻呂と真備は、留学生の代表ともいえる人物だったが、その一生は大きく違ったのである。