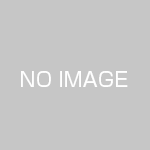関ヶ原の戦い
征夷大将軍・徳川家康 ~関ヶ原の戦い~
豊臣秀吉の死から2年余りたった1600年(慶長5)9月15日、美濃国(岐阜県)関ヶ原で、「天下分け目」とよばれる大合戦が始まった。
一方は、東から約10万の兵を率いて進んだとぐ川家康、これに対して西から進んでここに陣を構えたのは、石田三成を中心とする約8万の軍であった。それにしても、秀吉が切ない思いをこめて家康や三成に後事を託してから、わずかしか時がたっていない。それなのに、どうして、このような事態になったのだろうか。
例えば家康は、秀吉の葬儀が終わらないうちに、六男忠輝の嫁として奥州の大名伊達正宗の娘をめとることを約束している。秀吉は生前に、大名同士が勝ってに縁組をしたり同盟を結んだりすることを固く禁止していたが、家康は、それを平気で破ってしまったわけである。さらに家康は、福島正則・蜂須賀家政などの大名とも縁組した。この狙いが、有力な大名との結びつきを深めようとするものであったことはいうもでもない。それは、困っていた大名に救いの手を差し伸べるなど、他のさまざまな面でもあらわれていたのである。
これを見て心配したのは、秀吉の忠実な家臣であった石田三成である。「このままにしていたら、豊臣の天下はたちまち崩れてしまう」と考えた三成は、「家康殿、あなたのなさりようは、太閤さまのご命令に、そむくものではないか」と、厳しく抗議した。
しかし、家康は、いっこうにいうことをきかない。かえって、家康と三成との対立が目立ってしまうことになった。このようなこともあって、秀吉の死後2年間、家康は着々と勢力を固めていった。が、家康の方から天下とりの戦いをしかけたりはしなかった。むしろ、「そのうちに、三成が我慢しきれなくなって、戦いをはじめるだろう。そのときこそ、わが望みを一揆にとげるのだ」と、機会を狙っていた。そして、1600年、ついにその時がやってきた。
この年の六月、家康は、会津(福島県)の上杉景勝を討つための軍をおこした。「景勝は謀反をくわだてている。いまこそ、うちしたがえよ」と、諸大名に出陣を命じたのであるが、これが家康の本心であったかどうかは、疑わしい」むしろ、「自分が会津打倒に出かけて大坂を留守にすれば、きっと石田三成が、“家康打倒”の兵をあげるにちがいない。それこそ思うつぼだ」というのが、本心であったといわれている。その証拠に、彼は東海道をゆっくりと東へと進んだ。会津に近づいても、すぐには戦いをはじめようとはしなかった。
一方、石田三成は、家康が考えていたとおり、兵をあげた。「家康は、なき太閤さまの掟を守らないばかりか、太閤さまのご恩を忘れて秀頼さまを見捨てた。彼は裏切りものだ。いまこそ家康を討ちほろぼせ!」というのが、三成の言い分であった。この三成のうしろだてになったのは、中国地方で八ケ国・120万石をおさめていた毛利輝元である。
また、おもに西日本の大名たちが三成に味方するために集まった。これに対して家康方についた大名も多かったのだが、彼らにとっても「裏切り者」「秀頼さまに刃向う者」と非難されるのは、つらいことであった。多くの大名は、秀吉に取り立てられて今の地位に昇った者だったからである。
※文治派と武断派
豊臣秀吉に従った大名には、石田三成・小西行長・増田長盛らの文治派と、福島正則・加藤清正・池田輝政・藤堂高虎らの武断派とがあった。
文治派というのは、秀吉のもとで、主に作戦計画を立てたり、政治の方針を立て実施したりする人々。つまり作戦参謀のような人々であった。
武断派とは、前線で実際に戦う人々。つまり野戦軍の司令官のような人々であった。
ところで、この文治派と武断派は仲が悪く、何かと争うことが多かった。
朝鮮出兵のときにも、加藤清正と小西行長とが作戦や占領地の治め方などを巡って争ったし、さらに石田三成が小西行長の方をもって秀吉に讒言したため、秀吉が清正を罰するというようなこともあって、清正は両人をひどく恨んでいた。
秀吉の死後、この文治派と武断派との衝突を何とか抑えていたのが、五大老の一人前田利家であった。しかし、この利家が死ぬと、両派の争いは急に激しくなった。関ヶ原の戦いでも、主な武断派は家康方に、文治派は三成方についている。しかし、彼らの中には石田三成に憎しみをもっている者も多かった。「自分は、秀頼さまにそむくのではない。三成が憎いから戦うのだ」といって、自分自身を納得させているものもいた。
福島正則などは、家康から「大坂方につきたい者は、大坂にいてもよいぞ」といわれたときには、「もしあなたが、秀頼様の身を守り、もりたててくださるのなら、喜んで三成と戦いましょう」と答えたという。もちろんこのほかにも、「いずれは、徳川殿の天下がやってくるにちがいない。いまのうちに忠義に励んでおこう」と、家康方についた大名もいたことだろう。
さて、こうして関ヶ原の戦いがはじまった。小雨と深い霧の中に、鬨の声があがる。鉄砲の音が響く。両軍とも、懸命であった。押し寄せたり、押し返したり、勝敗はなかなかつかない。どちらかといえば、はじめは三成方の西軍の方が優勢であったという。家康は本陣で各方面からの報告を受けながら、いらいらするばかりであった。しかし、家康はいざというときにそなえての、とっておきの手を用意していた。西軍の中の何人かの大名と、「いざというときには、裏切りをして家康につく」という約束をしていたのである。
「その大名たちが裏切ってくれれば・・・」と願うだが、その知らせもまだこない。しびれを切らした家康は、ついに命令した。「小早川秀秋は、どうしたのだ。まだ、味方してこないのか・・・。しかたがない。鉄砲をうちこんでもよいから、早く味方するようにさせよ」西軍の小早川秀秋は、早くから家康と通じ、いざというときには東軍に味方すると約束していた一人なのである。関ヶ原の南方松尾山に陣をしいていた秀秋は、戦いの様子を山上からからながめて、約束を守るかどうか決めかねていた。しかし鉄砲を撃ち込まれては、もうじっとしているわけにはいかない。
ついに山のふもとに陣を構えていた西軍の大谷吉継の軍に向かって攻め込んでいった。そして、これをきっかけにして西軍はしだいに崩れはじめ、午後四時ごろには東軍の勝利が決定的になったのである。西軍を率いていた石田三成は、戦場をのがれて近江国(滋賀県)古橋村をさまよっていたとき、とらえられた。
しかし三成は、みじめな態度はまったく見せなかったという。そのことは、次のような話の中にもうかがえる。三成は、家康の本陣の門外にすわらせられていた。その前を東軍の武将達が通る。そのうちの福島政則は、仲の悪かった三成の姿を見ると、「なんだその姿は!おまえは役にも立たない戦いをはじめ、みじめにも負けて、とらわれ人になってしまっただはないか」としかりつけるように叫んだ。ところが三成は、少しも悪びれずににらみ返し、「私は、運悪く戦いに負けた。しかし、おまえ(福島政則)を生け捕りにできなかったのが、かえすがえすも残念だ」と、堂々と答えたという。また、西軍を裏切った小早川秀秋の姿を見つけたときには、「秀秋よ、私は不覚にもきさまの裏切りを見破ることができなかったが、おまえは太閤様のご恩を忘れて、はずかしくないのか」とののしった。そのために秀秋は、顔を赤くし、はずかしそうに通り過ぎていったといわれている。このような言い伝えは、三成がなき豊臣秀吉の恩を忘れず、自分は豊臣氏のために戦ったのだ」と、みずから誇りに思っていたことをよく示している。
真田日本一の兵
大坂城に入城した武将のうち、真田幸村は、関ヶ原の戦いのとき父昌幸とともに西軍についた大名である。このとき兄信之は東軍に味方し、冬の陣後、父や弟の助命に奔走したため二人は紀州九度山に蟄居していた。東西の手切れとなると、豊臣方はこの二人に入城を誘った。しかしそのとき父の昌幸はすでに臨終の床にあり、幸村に作戦を授けて世を去った。昌幸はまたためいきをつきながら「自分がこの作戦をいうのであれば、豊臣方はこれに従い戦いは且つであろう(昌幸は当時軍事略家として知られていた)。しかし、おまえがいったのでは、城中は従わないだろう。だからこの戦いは負けることになる」といったという。
案の定、幸村の意見は容れなれなかった。大坂落城の前日、真田幸村に率いられた二千人の赤備え(甲冑を赤く塗ってある軍勢)は、家康の首だけを目指して本陣に突入した。家康の旗本はこれを防ぎきれず、家康は命からがら逃げ出したといわれる。
所領を守った島津氏
関ヶ原の戦いにおける島津氏の立場は微妙だった。島津氏はもともと家康とも仲がよく、家康は上杉征伐に京を出発するとき、島津義弘に留守中石田三成が兵をあげることがあったならば、家康の守る伏見城を助けてほしいて頼んでいったほどだ。
しかし、西軍による伏見城攻めが始まったときに、約束した島津勢を、城中の家康勢は断ってしまったのである。家康の去った上方は、西軍一色である。というわけで、威島津勢も西軍に加わることになつてしまった。関ヶ原の戦いが始まっても、島津勢はじっと動かなかった。
そして、勝敗の帰趨が定まったころ、島津義弘は敵中を突破して帰国することを全軍に告げたのである。勝ちに乗じて島津勢に討ちかかる東軍の中を、勇猛で鳴らした島津勢は突進し、大部分の兵を失いながらも辛くも本国へ帰った。戦後、島津家は国を閉ざし、臨戦態勢を整えて家康と交渉した。島津家追悼が新たな内乱になることを恐れた家康は妥協し、島津家は領地をいっさい失わないですんだのである。
西軍が敗れたわけ
明治時代になって、日本の陸軍はドイツの参謀本部から派遣された将校によって指導を受けるようになった。あるとき、図上の作戦訓練として関ヶ原の戦いが教材となった。両軍の配置図を見たドイツの将校は、この戦いは西軍が勝利したに違いないと、言い切ったという。
たしかに両側を山に囲まれた狭い関ヶ原に、家康の東軍は侵入する。待ち構える三成の西軍は、関ヶ原に入口をふさぐようにそびえる南宮山に毛利氏の軍勢を置き、東軍は袋の鼠のような恰好になっている。しかし、この毛利軍は動かなかった。軍監として毛利軍を指揮していた吉川広家が、家康と通じ、一兵も動かさないかったのである。西軍の主力として最大の兵力を持っていた毛利軍が動かないものだから西軍の苦戦は必至である。しかも、西軍は本隊の南方松尾山に陣を敷いた小早川英秋が裏切ったのだからたまらない。数倍の敵を迎えて前線していた石田・宇喜多などの軍勢も、ついには壊滅してしまった。石田光成は、さぞ悔しい思いをしたことだろう。