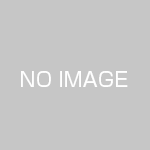西郷隆盛と征韓論
西郷隆盛の考え
西郷は、士族の行方を心から心配していた一人であった。と同時に西郷は、新しい政治の経緯に苦々しい思いをさせられてもいた。
彼に進言した鳥尾小弥太(もと長州藩 士・陸軍少将)は、その中で、「今や文明開化と称し米を父とし仏を母とし、みだりに風を移し俗をかえ、豪奢淫蕩、、、これまた弱士惰夫の国家を誤るもの」という意味を述べているが、西郷もまったく同感であった。
多くの志士の血を流して成就した維新であるのに、一部の政府高官のみが官尊民卑の頂点に立って高給をはみ、思うままの所業を重ねている。それに対して多くの士族の地位は、新政府樹立以来年とともに低くなり、落ちぶれていく運命にあるではないか。
西郷は「これでいいのか」という思いにかられていた。さらに、今こそ征韓を実施して士族の地位を高めるとともに、その戦いに乗じて、国内政治の変革を図るべきだという気持ちをかためていくようになった。
征韓論のおこり
征韓論は、このときにはじめてとなえられたものではない。新政府樹立当時からの課題の一つであった。
実は明治の初め新政府は、王政復古のことを鮮明に通告し、外交の開始を促していた。ところが鎖国政策をとっていた朝鮮は、その要求におうじない。むしろ、幕末に江戸幕に対してとった態度、つまり「日本は無法の国である。国内に入ることは一切許さない」という態度を取り続けていた。朝鮮がこのような態度をとったのは、「日本は、外交を口にしながら実は、朝鮮を征服しようとしているのではないか」という疑いをもっていたからである。
これに対し1871年(明治3)の初め、政府の命をうけて朝鮮の実情を調べた佐田白茅(さだ はくぼう)は、
「朝鮮が国書を受理しないのは日本を辱めるものであるから、その罪をとい、大使を送って一挙に攻め込めば、50日を出ずして国王を捕虜にできる。・・・同国は金穴であり米麦も豊であるから、日本の富強のもととなる。」
というような報告を提出している。
「朝鮮の無礼」を刻実に、このような征韓論を唱える人々は、明治初年には数多くいたのである。しかも戊辰戦争の終わりとともに、当時の国内には勝ち誇った兵があふれていた。ここの兵を朝鮮に向ければ、人々の注意を外にそらせるとともに、急速に高まりつつあった新政府への不満を和らげることもできるに違いない。
だからこそ木戸孝允なども、すでに1868年(明治1)12月ころには、岩倉具視に対して「韓国を討とう」という意味の進言をしているほどであった。
征韓論をとなえたわけ
西郷隆盛らが征韓論を唱えた1873年(明治6)は、農民の一揆が非常におおかった年である。1年間に56件も一揆が起こり、そのうち参加者が1マン人を超す大一揆が6件もあった。それは地租改正などに対する不満の現れでもあった。
こうした中で、西郷らは落ちぶれていく士族の運命を心配し、韓国と戦争することによって士族を兵士として韓国に送り、士族の不平不満を押さえようとした。またあわせて農民などの注意を外にそらそうとしたのである。
つまり西郷らは、1868年(明治1)に木戸孝允が征韓論を主張したのと同じような考えだったのである。
征韓論をめぐる争い
1873年(明治6)5月から9月にかけて、大久保利通・木戸孝允・岩倉具視ら政府の中心人物たちが、次々に欧米の旅から帰ってきた。2年にわたって欧米の国々を訪問し、日本とはくらべものにならないほどの文明の高さに、あらためて目をみはってきた人々である。その土産話を、留守を守っていた西郷隆盛・板垣退助・江藤新平・後藤象二郎・副島種臣らに熱心にはなして聞かせようとしたのだが、しかし彼らは、必ずしも帰国した人々を暖かくむかえようとはしなかった。表面では、「ご苦労さまでした」といいながらも、「まずいときに帰ってきた。もう少しゆっくりかえってくればいいのに」という態度がみえみえだったのである。
というのも、このころ政府の内部では、西郷らを中心にして「韓国を討て」という征韓論が高まり、間もなく軍事行動を起こすというところまで計画が進んでいた。けれども帰国した岩倉・大久保・木戸らがこの計画に反対するのはわかっている。そこで、「もう少し帰国がおくれれば、計画がそのまま実行できるのに・・・」という気持ちが強まっていたのであった。