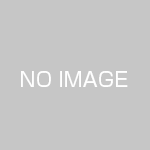西国の勇者 ~大内氏VS尼子氏~
西国の勇者 ~大内氏VS尼子氏~
16世紀の初めといえば、東国では北条早雲や斎藤道三が、その力と策略をもとに「国盗り」を進めていたころである。その同じころ、西国筋では、出雲国(島根県)の富田城を本拠とする尼子氏と、周防国(山口県)の山口を中心に勢いを広げる大内氏とが、二大勢力として対立していた。尼子氏は、はじめ出雲の守護代という地位にあったが、やがて守護の京極家をやぶって、山陰地方一帯に勢いを振るうようになった戦国大名である。ここに豊富にあった鉄資源も、その勢いのもととなっていた。
そして16世紀の初め、その尼子氏を率いるようになったのは、多少思慮に欠けるといわれながらも、勇猛の評判の高い尼子晴久であった。
一方の大内氏は、古くから多くの国の守護を兼ね、中国路から北九州一帯に勢いを振るった名門であった。将軍足利義満にそむいておこした応永の乱(1399)によって、一時勢いが衰えたが、応仁の乱では西軍の中心になって戦うなど、再び往時の勢いを取り戻してきていた。その勢いの重要な要因の一つは、莫大な利益をもたらした中国(明)との貿易にあった。また代々の当主は、都の文かを取り入れることに熱心で、その城下町山口は小京都の評判が高かったし、都の公家や芸術家で山口を訪れた者も数多い。水墨画家雪舟が、大内氏の援助で中国に渡り、帰国後は山口の雲谷庵にこもって制作に没頭したことも、その表れといえる。
この大内氏はね16世紀の初めの1528年(享禄元)、大内義隆によって率いられることになった。時に義隆は22歳。周防・長門・安芸・石見・備後・筑前・豊前七ケ国の守護を兼ねる大大名であった。互いに国境を接する尼子・大内の両氏は、しばしば対立し戦いあった。1542年には、大内義隆みずから大軍を率いて尼子討伐に向かうという出来事も起こっている。
ただこのときは、尼子方の強い抵抗や、大内方の武将の寝が入りなどがあって、大内氏の惨敗に終わった。このとき毛利元就は大内氏に組していたが、尼子の軍に追い詰められ、命からがらその居城・郡山城に逃げ帰るほどだったという。
戦国大名
戦国時代に、全国各地に割拠した大名を戦国大名といっている。戦国大名にはさまざまな型がある。
成り立ちによって分けると次のようになる。
〇守護大名から戦国大名になった人々
室町幕府から守護に任じられ、そのまま戦国時代も勢力をもって、戦国大名に成長した。
甲斐の武田氏、駿河の今川氏、薩摩の島津氏
〇守護代やその一族のように守護の家来でありながら、実際に国を支配しているうちに、しだいに 戦国大名に成長していった人々
越前の朝倉氏、越後の上杉(長尾)氏、尾張の織田氏など
〇在地の国人層から成長して戦国大名になった人々
安芸の毛利氏、土佐の長宗我部氏
〇下克上の極みともいうべき、全くその土地に縁がなかったのに戦国大名に成り上がった人々
美濃の斎藤氏、相模の後北条氏