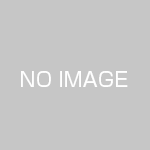黒船来航と日本
黒船来航と日本
17生気の初め、つまり江戸幕府ができた前後には、ヨーロツパではイスバニア(スペイン)、ポルトガルなどの勢力が強大であり、アジア各地への進出にも積極であった。その波は日本にも及んできたのだが、やがてオランダがそれに代わり、この地域での貿易におおきな力を発揮するようになる。鎖国時代の日本が交渉をもったのも、このオランダであった。しかし、19世紀になると、対外関係は新しく、また激動ともいえるような展開をみせることになった。
(19世紀の世界地図)
19世紀のイギリスは工業化による生産力の増大により得た、圧倒的な経済力と軍事力で世界の覇権を握った。イギリスは時には武力をも用いて世界各国に自由貿易を認めさせ、イギリスを中心とした国際経済体制に世界を組み込んでいった。
日本でも1853年、アメリカのペリーが浦賀に来航、江戸幕府に開国を認めさせ、日本も欧米を中心とした世界経済に組み込まれた。1868年には長らく続いた幕藩体制は崩壊し(明治維新)、新たに発足した明治政府は欧米文化を摂取して急速な近代化を目指した。19世紀末には、近代化に成功した日本やタイ王国などの一部の国以外は、西欧列強の植民地にされるか、強い影響下におかれた。
ペリーの態度
実は、幕府の要路にあった者たちは、ペリーの来航をあらかじめ知っていた。オランダ商館長が、その前年に
通知してきていたからである。しかし鎖国政策を継続して異国船内払令まで出し、実際にも、これまでに来航し
た外国船を数度にわたって退けてきた幕府は、ペリーも同じように追い返せばよいと考えていた。
しかし、ペリーの態度はそれまでに経験したことがないほど強硬であった。幕府の役人が旗艦サスケハナ号を
訪ねても、彼は顔をみせようとしない。部下に命じて、「提督は、最高の役人以外にはお会いしない、早く陸に
戻りなさい」といわせる有様である。
また、日本の役人が、「わが国の決まりで、ここでは国書を受け取ることはできません。もしここで受け取ったとしても、返事は長崎でなされることになります。したがって、すぐ長崎へおいでなさい」と指示しても、それに従おうとはせず、「どうしても承知してくれないのなら、わが提督は兵を率いて上陸し、江戸まで出かけて行って、将軍とじかにお会いするつもりです」と言い張る始末なのである。
ペリー提督
蒸気船を主力とする海軍の強化策を進めると共に、士官教育にあたり、蒸気船海軍の父とたたえられ、海軍教育の先駆者とされている。
嘉永6年6月3日(1853年7月8日)、浦賀に入港した。7月14日(6月9日)幕府側が指定した久里浜に護衛を引き連れ上陸、戸田氏栄と井戸弘道に大統領の親書を手渡した。ここでは具体的な協議は執り行われず開国の要求をしたのみで、湾を何日か測量した後、幕府から翌年までの猶予を求められ、食料など艦隊の事情もあり、琉球へ寄港した。
中国で太平天国の乱が起こり、アメリカでの極東事情が変化する中、嘉永7年1月16日(1854年2月13日)に旗艦サスケハナ号など7隻の軍艦を率いて現在の横浜市の沖に迫り、早期の条約締結を求め、3月31日(3月3日)に神奈川で日米和親条約を調印した。またその後、那覇に寄港して、7月11日、琉球王国とも琉米修好条約を締結した。
ペリー提督の態度 2
実は、ペリーがそのような態度をとるには、わけがあった。強い責任感わもっていたペリーは、大統領フィルモアから日本へいけと命令されたとき、たくさんの本を買入て、日本についての研究をしたという。そして、その研究の結論の1つとして、つぎのような考えをもつようになったというのである。「日本人は、外国人のことを軽蔑し、“われわれこそは、世界で最もすぐれた民族だ”と思い込んでいる。この日本人を相手にするときには、頼みこんだり要求を通してくれとお願いしたりするような態度では、うまくいかない。むしろ、こちらのほうが堂々とふるまい、相手に尊敬させるようにしたほうがよい。ときにはもっと強い態度に出て、高慢の鼻をへしおってやることが効果的で。」
日本にきてからのペリーは、この結論の通りに行動したのであった。そしてこのペリーの計画は見事に成功した。幕府の役人は「ペリーの態度は、これまでにきた外国人とは違う。もしうっかり扱うと、武力で立ち向かってくるかもしれない。そうなったら大変だ。特にここは江戸に近いから、江戸を砲撃でもされたら大騒ぎがおこってしまう」と心配するようになったのである。
その心配の底には、清(中国)でのアヘン戦争のこともあった。幕府はすでに、大国と信じ大いに尊敬もしていた清が、この戦争では、イギリスの近代的な武力の前に散々な目にあわされたことを知らされていたのである。その二の舞を踏むことになっては大変だという気持ちもつよかったのだろ。
※産業革命
1760年代から1840年代にかけて、イギリスでは、特に紡績業・織物業を中心に生産の仕方が大きく変わった。それまでの主に人力で動かす道具に代わって、水力・蒸気力で動かされる機械が次々に発明され、生産高が急に延びていくことになったのである。わずかな間に、生産高が27倍にもなったほどだというわれている。
こうして産業革命が進むとともに、機械を備えた工場が各地にでき、多くの労働者がそこで働くようになった。また、都市や商業が発達し、人口が増えるなど地域の様子や人々のくらしぶりまでもが大きく変化することになった。
その一方、工場の仕事をするためには大量の原料が必要となる。そこで検量を求めるために、また工場でつくられたたくさんの製品を売りさばくため、海外に進出することも増えた。
このような産業革命は、間もなくイギリスからフランスへ、そしてアメリカへも広まっていった。そして18世紀から19世紀にかけての欧米諸国のアジア進出を即したのであった。
○久里浜応接館
ペリーはついに浦賀に上陸し、幕府の当事者と会談することに成功した。その様子について当時の記録は、次のような意味のことを記している。「船から上陸した300人余りの兵隊たちは、銃をもって二列に並んだ。まわりには日本の武士もたくさんいるのだが、なにしろ米兵は身体が大きく服装も立派なので、ひときわ目立つ。やがて士官が大きな声で号令をかけると、300の兵がピカリと剣を抜いて銃につける。さらに次の号令で、さっと左右にわかれた。その間を、ゆうゆうと歩いて先頭にでたのがペリーである。彼は、蘆名美を揃えて進300人の行列を従えながら、久里浜応接館に向かって進んでいった。」
威勢を誇示しようとするペリーの意図が、よくわかるような演出ぶりだったのである。
さらに会談の場でも、米兵は次のような態度を示したという。「幕の中に入った米兵の一行は、ただちに入口のところに見張りを立て、6.70人の者は上段の間にまで進んで、ペリーをはじめ上官たちを守ろうとした。い
ずれり兵も剣に手をかけ、弾を込めたピストルを構て、すわというときには、すぐにでも戦えるという勢いである。これに対して、下座にいた日本の武士たちは、米兵の勢いに圧倒されるばかりであった。」
あわてる人々
浦賀でのペリーとの会見は、外国船に対するそれまでの幕府の態度を大きく変えさせる出来事であった。しかも、異国船は江戸のすぐ近くまで来ているのである。もし交渉が決裂したり、不足の辞退が起こったりしたら、アヘン戦争のときのような参事が起こらないとも限らない。そこで幕府は、万一の場合にそなえ、えどにいる大名に対してつぎのような命令を出していた。
「もし異国船が江戸近くの海まで進み、事件が起こりそうになったときには、老中が命じて早半鐘を打ち鳴らせる。すべての火消屋敷では、それを受け継いで同じ半鐘を鳴らすようにせよ。また半鐘がなったなら、各大名は、いずれも火事装束で城にのぼるか、定められた持ち場、持ち場を固めるようにせよ」 さらに一般の武士や町人に対しても、早板木を打ち鳴らせ。。そのときは、すわ大事が起こったと考え、あらかじめ命ぜられている持ち場へかけつけよ。また町家の者は、すぐ妻子を引き連れて、目的地の方へ立ち退くようにせよ」
とふれていた。こういう命令が出たのでは、江戸中の人々が驚きあわてるのも無理はない。「下様のよるもさわるもびくついて 早半鐘のいまかいまかと」と狂歌にうたわれる騒ぎになった。
狂歌といえば、次のようなものもある。「太平のねむりをさます上喜撰(蒸気船)たった四はい(四隻)で夜もねられず」上喜撰とは、お茶の名である。つまり、「太平の世になれ、眠りこけているような世の中だが、上喜撰をたった四杯飲んだだけで(蒸気船がたった四隻きただけで)すっかり目をさまされ、夜もねむれないようなだらしなさだ」とひにくっているのである。「馬具馬具師アメリカさまとそっといい」という川柳もつくられている。これは、すわ戦いというので、武士たちが争って武器や馬具を買い入れた様子をよんだものである。
このころ、太平の世が続いたこともあって、武器や馬具をもたない武士が多かった。そうした武士が争って武器や馬具をてにいれようとしたので、ふだんな10両ほどでかえたものが、7.80両にもなったという。武器や馬具を売る商人が喜んだのも当然のことで、彼らは表面では、「大変な世の中になつたものだ」といいながらも、内心では、「アメリカさまさまだ」と、ありがたがっているというのである。
また、「異国船地獄で猿がくやしがり」というものもあった。猿とは朝鮮出兵をして明(中国)までも従えようとした豊臣秀吉のことである。作者は、幕府や大名などのあわてぶりに憤慨し、この様子を地獄で見ている豊臣秀吉はさぞくやしがってるだろうと、この川柳をよんだのであった。