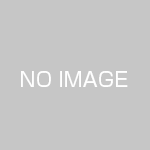聖武天皇と仏教
聖武天皇と仏教
唐へ渡った人々などを中心にきずかれていった奈良時代の文化を、年号にちなんで天平文化とも呼んでいる。
その「天平」の年号が定められたのは聖武天皇のときであり、天平文化もまたこの聖武天皇のころに、絢爛たる華をひらかせたのである。
聖武天皇は、文武天皇の皇子として生まれ、首皇子といった。父文武天皇がなくなったとき(707年)には7歳の幼さであったので、その成人をまつためもあって、元明・元正の二女帝が皇位についた。聖武天皇が即位したのは、724年(神亀1)のことである。その聖武天皇は、特に仏教の興隆に力を入れた。
律令を基本にする政治の方針は儒教にあったのだが、天皇はそれを尊重しつつも、さらに仏教を重視する政策によって国家鎮護、つまり国の安定と繁栄をはかろうとしたのである。
そのことは、天皇自身が記したといわれる次の言葉にもよく表れている。
「自分は政務のこたわら、さまざまな書物を読んでみたが、身を全し寿命を延ばし、国民生活を安定させていくには仏教が最上である。したがって自分は仏教を大事にし、ひたすらこれに帰依するのである」
その天皇の后、光明皇后もまた、仏教を深く信じた。
皇后は施薬院を置いて病人の治療にあたったり、非田院を設けて孤児や貧しい者に食料を与えられたりしたという。さらに、次のような話も伝えられている。
「皇后は、貧しい人を風呂によび、みずからその身体を洗ってあげた。ところが千人目にあらわれたのは、身体中うみただれた病人であった。皇后は、そのうみを吸出し、きれいにしたが、そのとき病人は、光輝く仏となって、天にのぼっていった」
これらのことも、仏教への深い帰依の姿を伝えているものということができるだろう。
国分寺の造営
仏教によって国家鎮護を果たしたいという天皇の願いは、たびたびの写経・造仏の命になってもあらわれている。
例えば、
◎737(天平9)3月、国ごとに釈迦三尊像をつくり、大般若経一部を写される(これは、その2年前からの天然痘の流行や凶作に対して、仏の加護を祈ろうというもの)。
◎740念6月、国ごとに法華経十部を写させるとともに、七重塔一基をつくらせる。
◎同年九月、国ごとに観世音経十巻を写させるとともに、高さ七尺の観世音菩薩をつくらせる。
などである。
そして741年2月には、国ごとに国分寺造営を命じる詔がだされることになった。その詔には、次のような意味のことが記されている。「この数年は凶作がつづき、伝染病が流行した。これは、自分に罪が多いためであろうと、はずかしさとおそろしさで、心も落ちつかなかった。そして、国民の幸せのために、なんとかしたいと考え、各地の神社を修理させたり、諸国に丈六(一丈六尺=約5メートル)の釈迦如来像をつくらせ、大般若経を写させたりした。お蔭で、今年は、天候もよく作物は豊かにみのった。このように神仏の霊験があらたかであるなら、この後もますます神仏をとうとばなければならない。
金光明最勝王経によれば、「もし、この経を大切にし、広くひろめる国王が出るならば、われら四天王は必ずその国を守り、一切のわざわいを取り除くとともに、すべての願をかなえ、喜びにみちた暮らしを約束しよう」と書いてある。いまこそ、国々は、それぞれ七重塔をつくり、金光明最勝王経・妙法蓮華経各十部を写すべきである。
自分もまた、紫の紙に金文字で金光明最勝王経を写し、塔ごとに一部ずつおさめたいと思う」
この詔にもとづいて、国ごとに、金光明四天王護国之寺(国分僧寺)・法華滅罪之寺(国分尼寺)がつくられることになったのである。しかし、この国分僧寺のためには、「好所を選び」という条件に合う二町(約220m)四方ほどの敷地をもとめ、高さ50mを超えるような七重塔をはじめ、金堂・講堂などの建物をつくりあげていかなければならない。
また一方で、多少の規模は小さくなるが国分寺もつくらねばならない。命をうけた諸国の国司・郡司は、技術者をよび建築資材を集め、徭役の農民を督励するなど、たいへんな努力を強いられたのではなかろうか。また地域の有力者が、この工事のために何らかの寄進をすることもあった。そのあとは今も、国分寺跡から出土する文字瓦(寄進者名・地名などが刻まれた瓦)に残されている。こうして国分寺は、その国々によって曲折を経ながらも、奈良時代松ごろには各地で完成していたらしい。
先の詔の中で聖武天皇は、「造塔の寺は、兼ねて国の華なり」と記したが、まさに国分寺とともに天平文化の枠は地方にもおよび、その「華」は地方に人々に、天皇や仏教のありがたさへの思いを強くさせていったに違いないのである。
大仏づくり
紫香楽宮ではじまった大仏づくりは、やがて中止され、2年後には、いま大仏がある場所で工事が再開された。
このときも天皇は、光明皇后とともに、みずから衣のそでに土をつつんで運び、土台をつき固めたといわれている
このとき、大仏づくりの中心になったのは国中公麻呂であった。公麻呂の祖父は、7世紀中ごろにほろんだ百済の高官国中弁成の一族である。彼は百済からの渡来人の子孫であったが、幼いころから仏像つくりに興味をもつとともに、さまざまな技術を身に着けていたらしい。しかし、高さ16mもの大仏を銅でつくるということは、中国にも例がない。「一体、どうやってつくればよいのか」と、まったく見当もつかない有様であった。
公麻呂らは、研究に研究を重ね、やっと一つの結論を出した。
◎まず、つくりたい大仏とまったく同じ大きさ、同じ形の原型を、粘土でつくりあげる。
◎この原型のまわりに銅を流し込み、大仏の姿に仕上げていく。
これは、頭の中で考えたとおり、簡単にいく仕事ではない。しかし、計画はただちに実行にうつされた。
大仏の原型をつくるためには、林のようにたくさんの柱をたて、横木をわたして、骨組みをつくらなければならない。どの木も、たくさんの人で運ばなければならないほどの大木だから、一本運ぶにも、つりあげるのにもたいへんな労力がかかった。
次には、骨組みを、蔦や竹でかこって、大体の形をつくりあげ、さらに粘土をあつく塗りつけて原型を仕上げていく。そのころ、大仏づくりに働いているのは、工事現場にいる人たちだけではなかった。奈良のまわりの国々では、多くの人たちが大木を切り出すために、山にはいっていた。
伐り出した木を運ぶ人もいる。一本の大木に何百人もの人々がとりついて、「エーンヤ、エーンヤ」と少しずつ動かしていくのである。おそらく、木を切り、運び、工事現場へもってくるだけでも、のべ何百万人という人が働いたのではないだろうか。
そのほか、粘土を堀出して運ぶ仕事、遠くの鉱山から銅をはじめさまざまな金属を運んでくる仕事、木炭をつくったり運んだりする仕事など、数えきれない仕事がある。それらの仕事にも、たくさんの人々が働いていた。まさに、国全体あげての大工事になっていたのである。
工事を初めてから1年2か月後、大仏の原型ができあがった。746年(天平18)10月のことである。
そして、このあとは、あらかじめ運ばれていた銅・白鑞(鉛と錫の合金=はんだ)・木炭などをもとにして、銅を流し込む仕事が始まった。これも決してたやすい仕事ではない。
まず、銅をとかすための炉を、大仏のまわりに築いた土手の上の各所にすえつけなければならない。そしてたくさんの炉に、いっせいに火が入れられる。木炭を真っ赤に燃やしながら、10時間以上もふいごで風を送りつづけるのである。おそらく、炉のまわりで働く人たちは、真っ赤な焔とふきあげる煙で、赤鬼のような姿になったにちがいない。とけた銅を流し込むときも、細心の注意が必要である。もし、原型に水でもしみこんでいると、おおきな音をたてて爆発を起こす心配がある。事実、そのような事故が、たびたび起こったのではなかろうか。こうして747年9月から749年の10月まで、8回にわたって銅の流し込みが行われたそして、いよいよ大仏をおおうように築かれていた土手が、取り除かれることになった。
土が取り除かれるとともに廬舎那仏が少しずつその姿を現してくる。何年もの長い間、工夫に工夫を重ね、幾日も眠らないほどの努力をつづけながら、全精力をつぎこんできた大工事であった。
国中公麻呂をはじめ、この工事にたずさわってきた人々は、しだいに姿を現す大仏を、どんな気持ちで見つめたことだろう。
開目供養の日
752年(天平勝宝4)4月9日、大仏殿のまわりには4千人の武人で守られ、一帯は美しく飾りたてられていた。大仏殿をかこむ回廊のあたりは、灌頂幡(かんじょうばん)という色あざやかな旗が30数本も立てられ、そよかぜになびいていた。大仏殿の中にも、同じ灌頂幡が並べられていたし、床一面には造花の花がまきちらされている。大仏の前には、数かぎりない生花が供えられ、なんともいえない香りにみちみちている。その大仏殿をめざして、1万人をこえる僧が、色とりどりの衣を身に着け、朝はやくからつめかけていた。僧ばかりでなく、立派な礼服を着た朝廷の高官も、次々に到着する。
この日、大仏はまだ完成していなかったが、病におかされていた聖武太上天皇の切なる願いで、開眼供養が行われることになったのである。
大仏完成の日を心から願し、開眼の日にはみずから筆をとって、仏眼に墨を入れようと楽しみにしていた聖武天皇は、体のおとろえもあって、すでに天皇の位を退き、太上天皇になっていた。その聖武太上天皇も光明皇太后や孝謙天皇とともに、さだめの席につく。一段高い座について開眼の筆をとるのは、聖武太上天皇のたのみを受けた菩提僧正。日本に来てから20年以上にもなる49歳のインド人の僧であった。
僧正の持つ筆からは、紫と白の長い綱がのび、聖武太上天皇をはじめ光明皇太后・孝謙天皇、そして道内に居並ぶ多くの人たちの手に、しっかりと握られていた。やがて僧正の手は静かに動き、大仏の目に墨を入れる。この開眼によって、これまでは単なる銅像であつた大仏に魂が呼び込まれ、生きた仏となるのである。この日にこの時を待ちに待っていた聖武太上天皇は、あふれる涙で大仏の顔も僧正の姿も、さだかに見えなかったのではないだろうか。
このあと、一万人の僧がいっせいに国の安全と発展を祈る経を読みあげた。さらに大仏殿の外の舞台では、いさましい舞、美しい舞が次々とまわれた。つづいてかなでられた音楽の中には、唐をはじめ、ベトナムやカンボジアのものもあったという。こうして、「仏教が二本に伝わって以来、この大仏の開眼の儀式ほど盛大なものはなかった」といわれた儀式が終わった。
しかし、この大仏をつくるために力をつくし、汗を流して働いたたくさんの人たちは、どうしていたろうか。一帯に響く読経の声や音楽にさそわれて近づいても、武装した兵士に追い払われるばかりであった。天皇と天皇をとりまく高位の貴族、そして役人たちが中心であったころの政治・社会の仕組みでは、実際に働く多くの人々が報われることは、少なかったのである。