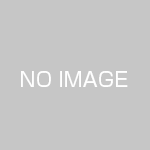大坂の陣
大坂の陣
家康は、諸大名をおさえるために、特に力をつくした。しかし、どうにも気がかりでならない大名が一人いた。もちろんそれは大坂城にいる豊臣秀頼である。このころ秀頼は、摂津・河内・和泉(いずれも大阪府)の三カ国に、65万石の領地をもつ大名になってしまっていた。大きな権力をもった家康から見れば、たくさんいる大名のうちの1人として、無視してもよいはずのものであった。ところが、力の差はありながらも、秀頼の背後には、少し前まで「天下人」として力をふるった父豊臣秀吉の威光がある。全国の大名の中にも、秀吉の跡継ぎということで、秀頼に心をよせる者が少なくないのである。げんに、1608年に秀頼が、疱瘡という病気になってときには、福島正則はじめ秀吉の恩を受けた大名たちが、こっそりと見舞いにかけつけてもいる。そればかりではない。大坂城には、秀吉が残した金銀財宝あるいは武器・弾薬などが数多く残されていた。また、秀吉がその全力を傾けてつくりあげた大坂城は、まことに堅固な城でもあった。「もし秀頼が旗あげしたら・・・」「大坂城にたてこもって、徳川氏にそむくようなことにでもなったら・・・」という家康の心配は、ついに「早いうちに秀頼をほろぼしてしまうにかぎる」という固い決心へと変わっていくことになった。
しかし、さすがの家康も、秀頼に対して、簡単に手を出すことはできない。はじめのうちは、秀頼やその母淀君が近畿地方各地に寺や神社を建てたり、修理したりするのを見て、「それはよいことです。ぜひ、おやりなさい」とすすめたりしていた。もちろんそれが家康の本心ではない。「寺や神社のためなら、おおいに金を使わせておけ。大坂城の金銀がすくなくなるのは結構なことだ」と内心ほくそえんでいたのである。と、そのうちに、ついに豊臣方をいためつけるための、またとない出来事が起こった。方広寺の鐘銘事件と呼ばれるものが、それである。
≪方広寺の鐘≫
「国家安康」の鐘は現存して重要文化財に指定されており東大寺、知恩院のものと合わせ日本三大名鐘のひとつとされる。大仏殿は、2000年(平成12年)発掘調査により東西約55m、南北約90mの規模であったことが判明している。大仏が安置されていた場所からは八角の石の基壇も発掘されている。基壇に使われた花崗岩の切り石の多くは、明治6年に京都市の内外に京都府により築造された6基の石造アーチ橋の建材に転用された。大仏殿のあった場所には明治になって豊国神社が建てられた。門前の餅屋が売っていた「大仏餅」は大仏を型押しした餅で、大仏を訪れた人々のよい土産となった。この餅屋には石川五右衛門が住みこんでいたという伝説がある。鴨川河原まで通じる抜け道もあったという。門前、餅屋があった向かい辺りには、秀吉が築かせた耳塚がある。
こうしてはじまったのが1614年10月の“大坂冬の陣”である。「いよいよ、戦いのはじまりだ」というとき、家康は73歳の老人とは思えないほどイキイキしていたという。当時の記録にも、「(家康は)それまで病気がちで元気がなかったのに、開戦がきまると同時に、急に若返った」というような意味のことが記されている。おそらく家康の心の中は、「この戦いに勝てば、まちがいなく徳川の天下になる。わが望みもはたされるわけだ」という思いが高まり、それが若さを取り戻すもととなったのであろう。
しかし、大坂城の守りは固かった。攻めての家康方の軍は20万人、これに対して城内には10万人の兵しかいない。しかもそれは、真田幸村・後藤又兵衛・塙団右衛門(ばんだんえもん)など、徳川の世になって没落した大名や、没落した大名に仕えていて浪人になった武士たちがほとんどである。
けれども、外堀・高い石垣・じょうぶな塀や櫓、そして内堀など、二重三重に守られた大坂城は、いくら攻めても攻め落とすことはできなかった。「これでは、戦いが長引くばかりでなく、損害も多くなるだけだ」と考えた家康は、ひとまず講和をすることにした。といっても、もちろん大坂城攻略をあきらめたわけではない。「講和」をきっかけに、大坂城の守りを酔われてしまおうと考えたのであった。そのはかりごとは、講和の取り決めをむすんでからまもなく、次のような形であらわれた。
こうしてはじまったのが1614年10月の“大坂冬の陣”である。「いよいよ、戦いのはじまりだ」というとき、家康は73歳の老人とは思えないほどイキイキしていたという。当時の記録にも、「(家康は)それまで病気がちで元気がなかったのに、開戦がきまると同時に、急に若返った」というような意味のことが記されている。おそらく家康の心の中は、「この戦いに勝てば、まちがいなく徳川の天下になる。わが望みもはたされるわけだ」という思いが高まり、それが若さを取り戻すもととなったのであろう。
しかし、大坂城の守りは固かった。攻めての家康方の軍は20万人、これに対して城内には10万人の兵しかいない。しかもそれは、真田幸村・後藤又兵衛・塙団右衛門(ばんだんえもん)など、徳川の世になって没落した大名や、没落した大名に仕えていて浪人になった武士たちがほとんどである。けれども、外堀・高い石垣・じょうぶな塀や櫓、そして内堀など、二重三重に守られた大坂城は、いくら攻めても攻め落とすことはできなかった。「これでは、戦いが長引くばかりでなく、損害も多くなるだけだ」と考えた家康は、ひとまず講和をすることにした。といっても、もちろん大坂城攻略をあきらめたわけではない。「講和」をきっかけに、大坂城の守りを酔われてしまおうと考えたのであった。そのはかりごとは、講和の取り決めをむすんでからまもなく、次のような形であらわれた。
大坂の陣
家康の有力な家臣本多正信の子正純が、大坂城の外堀を埋める工事をはじめたのである。「外堀をうめる」ということは、講和の条件の中に、何気なくいれられていたものであった。しかも、本多正純は、外堀だけでなく内堀を埋める工事をはじめた。「それでは約束が違うではないか」といわれても、いうことをきかない。
「私は、父正信のいいつけで、この仕事をしているのです。もし、おっしゃりたいことがあるなら、父に申してください」というだけである。その正信に申し入れると、
「それは申しわけないことです。さっそく家康公の指図をうけますので、もう少しの間、お待ちください」
「いいではありませんか。もう講和が成立したし、この後は戦いの起こることはありますまい。このままにしておいても大丈夫ですよ。それとも、内堀や外堀をもう一度掘りなおして、戦いの準備でもなさいますか・・・」と、ごまかされたりおどかされたりする有様であった。
こうしてさすがの大坂城も、はだか城同然のありふれた城になってしまった。次の年(1615)四月、再び大坂城を中心に、戦いがおこった(大坂夏の陣)しかし、外堀や内堀を埋められた大坂城は、おしよせた30万の大軍をささえることはできなかった。それでも大坂方の武士は、力をふるって戦ったという。特に、真田幸村の率いる軍は、二度まで家康の本陣に迫り、家康をあわてさせたほどであった。激しい戦いは一か月以上も続いたが、5月、ついに大坂城は燃え上がる炎につつまれた。そして、城のあるじ秀頼も、その母淀君も炎の中で自害し、ついに豊臣氏はほろんでしまった。征夷大将軍になつて12年目、家康は、やっと徳川氏による天下統一の望みを完全に果たしたのである。