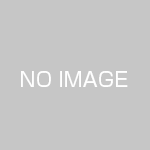万延元年遣米使節
万延元年 万延元年遣米使節
77人 留学生5人
使節など行った人
新見正興、村垣範正、小栗忠順、森田清行、成瀬正典、塚原昌義、
玉虫左太夫誼茂(仙台藩の人、随行記を書くが後に戊辰の役の責
任で切腹させられた人)
〇遣米使節団護衛・咸臨丸96
勝海舟・福沢諭吉
万延元年遣米使節は、江戸幕府が日米修好通商条約の批准書交換のために1860年に派遣した使節団である。
1854年の開国後、最初の公式訪問団であった。また津太夫一行以来、日本人として2度目の世界一周をした。 1860年2月6日、使節団一行は米国政府が用意した軍艦「ポーハタン号」に乗船し、江戸(品川)を出港。太平洋
を横断してホノルルに立ち寄り、同年3月、サンフランシスコに到着しました。勝海舟、福沢諭吉、ジョン万次郎等が乗船したことで知られる「咸臨丸」は、このとき、ポーハタン号の護衛として随伴していました。
サンフランシスコを出港した一行が次に向かったのは南米パナマでした。ここで彼らは、日本ではまだ目にしたこともない蒸気機関車に初めて乗車し、大西洋側のコロン(アスピンウオール)まで移動。鉄路を走る巨大な汽車は、使節達に大きな驚きを与えたといいます。そして、5月には再び蒸気船で大西洋を経てワシントンへ。使節団はここでブキャナン大統領と謁見し、条約批准書を交換しました。※ 福沢諭吉さんがでてきました。次回には通訳として参加します。
勝海舟 1823~1899
江戸で御家人勝小吉の子として生まれた。勝家は貧乏で、その日の食べ物にも困るような有様だったが、父・小吉は海舟の才能に望みをかけ、その教育に全力を尽くした。
やがて、海舟はその才能を認められて幕府に仕え、さらに長崎にできた海軍伝習所に学んで、洋式海軍の技術
を身につけた。彼が咸臨丸の艦長としてアメリカに渡ったのも、そのときの学習を見込まれてのことである。
咸臨丸
原名をヤッパン号といい江戸幕府がオランダに注文して造らせた軍艦である。1857年に長崎に回航されて
きた。長さ47m、幅7m余りの小さな蒸気船であるが、日本が手に入れたはじめての蒸気船である。
その船をほとんど日本人だけで操船しアメリカまで行き着いたことは、「その勇気といい、技術といい、これ
だけは日本国の名誉として世界に誇れることといえるだろう」と福沢諭吉が自慢したほどであり、日本人の優秀
さをよく示したものである。
玉虫左太夫・・・・仙台藩士
使節団正使・新見豊前守正興(にいみぶぜんのかみまさおき)の従者(随員)である仙台藩士・玉虫左太夫(たまむしさだゆう)は、「航米日録」(8巻)(航海日誌)という記録を残した。
左太夫は外国語の知識に欠け、海外事情にもそれまで無縁であった。だが、俊才の彼は儒学の素養と鋭い観察眼によって異国をつぶさに観察し、詳細かつ正確な記録を残した。比類ない観察記録といえる。左太夫は知的に、客観的に見聞を詳細に書き留めた(批判的記述は別の日誌に書き止め他見に供しなかった)。
米艦ポーハタン号乗艦から世界一周を果たして横浜帰港までの9カ月の間、果敢な取材や観察をもとに具体的数字を挙げて実証的に記述するその手法には類を見ない価値がある。彼は緻密で冷静な頭脳の持ち主であった。
「左太夫の『航米日録』は、その素直な感受性と率直な批判精神で書かれた得がたい外国体験の記録でり、無意味な強がりや偏見もない眼で、米国を見ようとした。彼は最初、米国を聖道のない国と考えていた。米国人を礼節をわきまえぬ国民と考えていた。その定太夫が、幕府の遣米使節の最下級の属官として米国船に乗りこんだのである。そして彼は、毎日の船旅で少しずつ、自分のこの考えが間違いであったことに気づいていく。
左太夫の目覚め
「日本を離れると、船はたびたび暴風にあった。属官である彼は正使、副使たちと違い、もっともひどい場所に起居していたため風波に持物を濡らし、ずぶ濡れになったが、その都度、親切に助け、慰めてくれたのは同乗した日本人の上司たちではなく、ほかならぬ米国人の下級船員たちだった。彼は米国人にたいする偏見がまず薄れたのはこの時である。
左太夫は、この船内で士官と水兵とが互いに助けあい、協力しあい、その交情の親密なことに気づき始めた。これは、彼が受けた儒教的教養にたいする最初の衝撃だった。米国人には聖道はないかもしれぬが、そのかわり人間的な暖かさがあると彼は気づいたのである。
『我国にては礼法、厳にして、総主などには容易に拝謁するをえず、少しく位ある者は…下を蔑視し、情交、かえって薄く、兇事ありといえども悲嘆の色を見ず』と彼は書いた。『しからば、礼法厳にして情交薄からんよりは、寧(むし)ろ、礼法薄くとも情交、厚きを取らんか』玉虫左太夫は厳しい儒学的教育を受けて育った侍だっただけに、この彼の反省は我々もしみじみと受け取れるのだ。
こうして太平洋を渡り米国に赴く船のなかで、左太夫の心には少しずつだが微妙な変化が始まった」
「属官である彼が、自分の船内観察や考えが上司に伝わるのを怖れて、自分だけの日記をつけだしたのもこの時からであった。その日記には、同船の日本人上司にたいする痛烈な批評も書き込まれている。たとえば、同船の日本人たちは船内の食事に不平を言いつづけているが、連中は平生は家にあっては一汁一菜しか食べていないくせに、こういう旅行の際には『俄(にわ)かに奢侈の言を発して美味を好む』とは不思議であると、彼は言っている。
左太夫の上司にたいする批判は彼自身が属官であるゆえんの不平も感ぜられないではないが、しかし、いかにも外国旅行に行く日本人的な性格を浮き彫りにしていて、今も昔も変わらない部分を衝いている。 『航米日録』には、初めて接する異国の人によって目ざめていく若い日本青年の心の変化が、手に取るように書かれている。(高橋哲郎著「幕末遣米使節随員・玉虫左太夫~近代への大いなる目覚めと挫折~ 」要約)
戊辰戦争責任を問われて、切腹となった玉虫さん、生きていたなら
どんなに良かったか。残念です。
後、1日の猶予があったなら、死なずにすんだかもしれないので、
残念です。優秀な方でした。
維新前夜の動き
文久3年(1863)、つまりペリー来航から10年余たったこの年、そして幕府の遣欧使節団が約1年ぶりに帰国したこの年は、国内では尊王攘夷の声と活動とがもっとも高揚した時であった。
尊攘の嵐
攘夷親征の動き ー真木和泉と攘夷親征ー
尊王攘夷運動のリーダーの一人であった真木和泉は、「今はすでに、幕府を相手にしているときではない。朝廷は幕府との縁を切ったほうがよろしい。むしろ、朝廷が幕府を倒して全国の土地・人民を支配し、天皇みずからが攘夷の先頭に立つべきときがきている。」と「攘夷親征」の論を強く主張し、多くの賛同を得ていた。
彼は、この年8月12日の日記に、「朝、三条実美公(朝廷における攘夷論の中心人物)と会い、さらに国事参政の地位にある方から、攘夷親征をを聞かされた。まったくの喜びである。」という意味のことを記している。
おそらくこの時点での真木和泉は、攘夷親征が直ちに実現するに違いないとの信念を強めていたのであろう。それは真木和泉だけでのとではない。尊王攘夷を唱える多くの人々の信念である期待ででもあったのである。
またこのころには、それを裏付けるような事実もあった。
この年の3月、第14代将軍・家茂が京都に行き、孝明天皇に従って「攘夷祈願」を加茂社で行ったこと、さらに朝廷の強い要求に押されて、「5月10日を期して攘夷を実施するる」旨の奉答をしたことは、その最大のものであったといえよう。幕府が、朝廷の指示に従ってその政策を決めるということは、幕府創設以来、かつてなかったことなのである。
家康の心配が的中
西国大名の動きを、死ぬ間際まで心配していた家康でしたが、幕末の結果をみるにつれ、心配は的中してます。長崎に貿易港ができていたたこともありますが、ここで奉行を勤めるとスゴイ貯金?ができるということです。それだけの利益があって、様々な外のリアルな情報もえられたでしょう。
鎖国とはいえ、幕府にはオランダからの報告書で外国の諸事情は入ってますし、四つの口、長崎、琉球、蝦夷、対馬という窓口はあったわけです。幕府が情報を独占していた時代が、江戸時代です。
以下は、以前書いたブログの再掲載になります。
1616年(元和2)正月、腹痛を起こしたのをきっかけに、一時は、食べ物がのどをとおらないほどになり、その後、よくなったり悪くなったりを繰り返した。
その間に家康も、死の近いことをさとったらしい。
形見分けをし、遺言を残している。
また、死の二日前には、三池典太(みいけひろのり)のつくった刀で罪人のためし切りをさせた。
そして、「切れ味のすばらしい名剣でございます。」という報告を受けると、その血刀を枕元において、「われ、この剣をもって、長く子孫をまもろう」といったという。
家康が死を目前にして、まだ心配だったのは、徳川氏の行く末であった。
このことは、「・・・東国の諸大名の多くは譜代のものであるから心配はないが、心にかかるのは西国大名の動きである。西国をおさえるために、久能算(静岡県)に祭るわが神像は、西に向けて安置せよ」と遺言したことにもあらわれている。
こうして家康は、1616年4月17日、75歳の生涯を終えた。