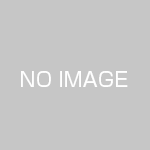崩れる地方政治の仕組み
崩れる地方政治の仕組み
中央で権力争いが続けられていたころ、地方政治にも大きな変化が生まれてきていた。その主な現れとして、私有地の増大、地方官僚の腐敗などをあげることができる。
☆耕地をふやす努力
朝廷が政治の基礎にしようとした公地公民・班田収受の仕組みは、生活に苦しむ農民が逃げ出すこともあって、少しずつ崩れはじめていた。と同時に、もう一つ大きな問題になっていたのは、国民に給与すべき耕地が不足しているということであった。その問題解決のために朝廷は、「食糧も道具も国で用意し、農民を一人あたり10日間使って、良田百万町歩を開墾する」という計画をたてている。722年(養老6)のことである。しかし、当時の水田面積は、全国で60万~70万町歩くらいのものであった。
それよりも広い水田を一挙に開こうなどということは、とうてい実現できるものではない。まさに、机上の空論であった。そのためもあって、翌年には、太政官から天皇に対して次のような意味の申し出がなされた。「近頃は、人口が増えて口分田を多く必要とするようになったのに、給与すべき田は不足しています。そこで、次のような恩典を与えて、水田の開拓を奨励したいと思います。
すなわち、新しく灌漑施設をつくって開墾する者には、その地の多少を問わず三代にわたって私有させ、もとからある施設を利用して開墾した田は一代かぎり私有させるようにしたいと存じますが、いかがでしょうか」というのである。
つまり、国家の手ではとうてい実効のある開拓ができないから、民間の活力を利用しようというのである。この願はただちに裁可された。こうしてできたのが、「三世一身の法」といわれるものである。この法がだされると、「よし、自分の土地がもてる」というわけで、荒地の開墾に乗り出す者がふえた。けれども少したつと、この三世一身の法の効果は、たちまちうすれてしまった。
「いくら苦労して開墾しても、年限がくれば、また国にとられてしまう。ばかばかしい。」というので、せっかく開墾した土地をほうっておいたり、開墾そのものにも嫌気がさしてしまったりする人たちが、多くなったからである。そのため、朝廷は、また新しい法を出した。743年(天平15)に出された、「墾田永年私財法」がそれである。
墾田永年私財法
墾田永年私財法というのは、
☆新たに開墾した耕地は、自由に使ってよいし、永久に私有してかわない。
☆ただ、だれでも、いくらでも私有してもよいというわけではない。身分や位によって、私有してよい広さを決める。という内容の決まりであった。
いうまでもなく、この法のねらいは、耕地をふやそうとするものであったのだが、もう一つ、この法がだされた743年という年の、国内の様子も考えてみる必要がある。実は、この前々念には、「国ごとに、国分寺と国分尼寺をつくるように・・・」という詔がだされている。
また、同じ743年の10月には、「毘盧遮那仏をつくろう」という詔がだされた。つまり、743年という年は、聖武天皇を中心とする全国的な造寺・造仏の仕事が、まさに始まろうとしていた時期だったのである。
そのような時期であっただけに、政治の中心になった人々は、次のように考えた。
「これだけの仕事を進めていくためには、どうしても、朝廷の貴族や役人、それに地方の役人や豪族の協力を得なければならない。そのためには、彼らが喜ぶようなことをする必要がある。どうすればよいか・・・」
その結果が、墾田永年私財法であったともいえる。
つまり「彼らはは、自分たちの土地をほしがっている。それによって、もっと楽な暮らしをしたいと願っている。その願をかなえてやれば、多少は無理があつても、造寺・造仏の仕事に協力してくれるだろう」というのが、この法をつくった人々の考えであった。なお、高知は私有させても、税まで免除するというわけではなかった。
だから、「たとえ私有を許しても、耕地はふえ、税もふえる。それに開墾した者も喜ぶ・・・。みんなにいいことではないか」という考えもあったことだろう。
こうして、墾田の私有がゆるされるようになってからは、都の貴族、大きな寺や神社、地方の有力者などが、争って開墾に励むようになった。
家来の者を未開地の多いところにいかせ、近くの農民を集めて開墾させる。その農民の中には、苦しい生活にたえられないで、住んでいた土地から逃げてきた者もたくさんいた。開墾によって私有するようになった耕地を荘園とよんでいるが、これは、明らかに公地公民の仕組みを崩すものであつた。
実は荘園は私有地であるが、税まで免除されたわけではなかった。
けれども、身分の高い貴族や勢いの強い寺院の私有地となると、税を集める役人も、あまり強くはものがいえなかった。
それに、これらの貴族や寺院は、もともと、位田・職田といった、税をおさめなくてもよい土地を与えられていた。新しく開墾した土地についても、「これは、もともと朝廷から与えられたものだ」といわれてしまえば、役人は手も足も出せなかった。さらに貴族や寺院の中には、朝廷と交渉して、荘園を免税地とするよう正式に認めさせる者もいた。
こうして全国に、免税の荘園がふえていった。
つまり、造寺・造仏の必要から法を変えたということが、やがて政治を乱すもとになっていったのである。
私腹を肥やす地方官僚
国司の権力は大きかった。例えば、戸籍をつくって、どのむらに誰がいるか、何人くらいの住民がいるかなどをはっきりさせ、税を取り立てる。また、戸籍にしたがって、口分田をわけ与える。兵士を集めて訓練したり、寺や神社の修理・監督などもする。罪を犯す者があれば、よく調べ裁判をして、罰をきめる。そのほか、国内をまわって、脳儀用の様子を調べたり、都の朝廷に報告書を出したりもした。
つまり、国司は、政治・軍事・産業・裁判などの、あらゆる面で権力をもっていた。この国司のもとで、もっとせまい地域の指図をしていたのが郡司であり、その下にいたのが里長である。国司が、都から派遣されてきた役人であったのに対し、軍事や里長は、もとからその地域に住みついていた人、しかも古くから勢力をもっていた、その地域の豪族であった。地域の様子もよくしっいたし、地域の人々の信望もあつかった人々である。
ところで、この国司・郡司・里長などが律令の決まりどおりに、きちんと政治をしている間は、まだよかった。
しかし、ときがたつうちに、国司の気持ちがだらけてくる。おまけに、都の朝廷がらは、「工事のために人夫を送れ」「税の送り方がおそいぞ」などといってくる。「地方の様子もよく知らないくせに、勝手なことばかりいうやつらだ」などど、気を高ぶらせる国司もいたろう。
そのうえ、暮らしなれた都の姿が目に浮かんだり、「こんなさびしい田舎で、いやになってしまう」と気をめいらせたりしたこともあったにちがいない。そのような状態の中で、国司の権力をふるって自分の利益を図り、私腹を肥やそうとする国司が増えた。出挙の仕組みを利用してたくさんの利息を取り立てたり、何かにつけてわいろをとったりする。また、もともと国のための仕事をするはずの徭役の農民を、自分用の耕地の開墾に使ったりするのである。なかには、租として集めた米をしまっておく倉庫に火をつけ、燃やしてしまったりした国司もあったという。といって、倉庫に米がはいっていたわけではない。稲わらだけをつめておいて焼き払い、「米は放火のため焼けてしまいました」と報告して、実際にも自分ものにしたのである。
さらに公廨稲(くがいとう)の制度が745年(天平17)にできたことも、国司がその収入をふやそうと画策するものになった。公廨稲(くがいとう)というのは、公出挙の利息(利稲)を、「さだめられたこと」に使ったあとは、国司(守介掾目)のあいだで分配してもよいというものである。
この「さだめられたこと」というのは、
・農民から取り立てた税(米)や出挙の利稲に、欠損がでたり未納があった場合に補填する。
・庸調を都に運ぶ際の輸送費に当てる。
ことであった。
だから、欠損・未納がないように税や利稲を厳しく取立たり、輸送費が安くあがるように工夫したりすれば、国司たちの収入もふえたわけである。その工夫が農民をいっそう苦しめることになったのはいうまでもない。ところで国司があくどいことをすれば、郡司もそれを真似るようになる。さらに、国司と郡司がシメし合わせて、私腹をこやすたくらみをすることも多かったことだろう。
一方、その郡司をおびやかすような問題も起こっていた。
農村には、私出挙による利益や墾田の拡大によって、新しい有力者が生まれ、古くからの家柄と勢力を誇っていた郡司と対立するようになったきたのである。
こうして奈良時代の後半には、生活に苦しんで逃げ出す農民、ふえふいく荘園、国司や郡司の不正、新しい有力者との争いなど、地方の政治の乱れが目立つようになっていった。
・・・・ん・・・、「倒れる国司は、ただでは起きない」って言われるほどだから、納得です。
勘解由使の設置
桓武天皇がおこなった政策の中に、勘解由使という新しい役職の設置がある。この当時、政治の仕組みは律令によって行われていたが、律令には定められていない役職もつくられるようになっいた。このような役職を令外の官というが、勘解由使もその令外の官のひとつである。勘解由使の仕事は、国司の交替の事務を円滑にすることであった。このころ、国司の引継ぎに当っては、多くの紛争や不正が起こっていた。というのも、国司の職には多くの紛争や不正が起こっていた。というも、国司の職には多くの利権がつきまとっていたから、任官した国司はできるだけ利権をあさって財を蓄えようとした。そのための横領などが、国司の交替のときに発覚して、紛争になることが多かったのである。勘解由使の役目は、国司の交替に当って、不正などが行われないように監督することであった。桓武天皇が、地方政治を立て直し、朝廷への収入が正しく行われるようにしようとしたことの表れである。
しかし、この勘解由使の制度も、しだいに有名無実になり、平安末期には名ばかりのものとなってしまった