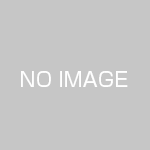悲劇の将軍頼家
☆将軍としての頼家
1182年(寿永1)8月12日、源頼朝の妻政子(北条時政の娘)は、玉のような男の子(万寿)を産んだ。
跡継ぎが編まれたというので、頼朝の喜びはひとしお大きかった。もちろん、源氏の安泰を願う御家人たちも、歓声をあげてこの誕生を喜んだ。
こうして万寿(のちの二大将軍頼家)は、周囲の人々のいつくしみと期待の中で、すくすくと成長していった。ことに乳母にえらばれた比企尼(頼朝の乳母だった女性)の娘、そして比企一族は、源氏の跡継ぎを育てるのに熱中した。
万寿は幼い頃から体格がよく、武芸にも優れていたらしい。「頼朝公にも勝る武勇の人だ」と書き残した本もある。
しかしその一方で、気が強く、神経質で、周囲の人々への愛憎の感情がはげしかったとも伝えられている。
その頼家は、父頼朝の死後、18歳の若さで将軍家を継いだのだが、とかく「自分は生まれながらの将軍だ」という意識を強く出しがちであった。
そのうえ、頼朝の跡をそのまま実行するというよりは、「まわりの者にわずらわされないで、思い切ったことをしたい」という気持ちも強かった。
妻の実家をたよりにして、舅の比企能員を重く用いたり、5人余りのお気に入りの家来を選び、「この五人のほかは、自分に目通りすることを許さない」などと言い出したりしたのも、その表れである。
母の政子や北条時政は、頼家のこのような性格・態度が心配になってきた。
「これでは、頼家の側近の者たちと、これまで命がけで幕府を助けてきた御家人たちとの間が悪くなるばかりだ。
それに、幕府に対する信頼も失われ、せっかくの頼朝や自分たちの苦労も無になってしまうに違いない」とも考えるようになった。
その心配をなくすために考えだしたのが、有力御家人による合議制の仕組みであった。
すべての政治や裁判にかかわることは、北条時政・北条義時・三好康信・大江広元・梶原景時・三浦義澄・和田義盛・比企能員など13人の合議によって決めるという政治体制をつくったのである。
それは、頼家が家督を継いでから三か月余りたったときのことであった。
比企氏の滅亡
やがて、頼家に対する北条政子・時政らの批判は、いっそう強まっていった。というのも頼家が、乳母そして妻(若狭局)の実家である比企氏(能員)と結びついて、その勢いを伸ばそうとしがちだったからである。しかも頼家の勝手な振る舞いは激しくなるばかりで、その評判もかんばしくない。
「頼家は、わが子であるけれども、いまのうちになんとかしなければ」政子は、しだいにこのように考えようになっていった。ちょうどそのころ、つまり頼家が家督を継いで、四年余りたった1203年7月、頼家が急に病気になって寝込むという出来事が起こった。この病気は、まもなく治るのだが、政子や頼家に反感をもっていた御家人たちは、この機会をのがさなかった。「将軍は、ご病気である」ということを理由にして将軍職をやめさせ、頼家の長男一幡を、関東28ケ国の総地頭および日本国総守護職に、頼家の弟千幡(のちの実朝)を、関西38カ国の総地頭職に任ずることにしてしまった。
しかしこの二人は、それぞれ6歳と12歳という幼さである。もちろん、直接に政治をとることなどできない。そのかわりに、政子と北条氏が、政治の実権を握ることになったのである。ところが、このようななりゆきに、頼家も彼を援助していた比企氏も、たいへん不満であった。このことについて『吾妻鏡』は、次のように書いている。
「病の床にふしていた頼家は、政子のやり方に強いいかりをもった。そして比企能員を呼び寄せると、『ただちに北条氏と千幡を討て』と命じた。ところが、この様子は、障子のかげにいた政子に、すべて聞かれてしまった。しかも政子は、頼家らのくわだてを北条時政に急報したのである。時政は、用事にかこつけて比企能員一人だけを自宅に呼び寄せて、その命を奪った。さらに一幡がたてこもっていた小御所を襲い、比企氏一族をほろぼしてしまった」『吾妻鏡』にあるこの記述が、本当のことであったかは、はっきりしない。しかし政子や北条氏が、この事件をきっかけに、競争相手であった有力御家人の一人、比企氏をほろぼしてしまったことは確かである。おな、このときのこととして次のような話が伝えられている。
比企氏が滅んだ次の日、つの館のあたり(いま比企谷とよばれている地域)一帯には、やけこげたにおいがたちこめ、敵味方の死体がちらばっていた。その悲惨な戦いのあとを、一人の僧が、念仏をとなえながら歩きまわっていた。僧は、かつて将軍頼家の相手をして蹴鞠などをした源性であったが、6歳でこの戦いにまきこまれた一幡(頼家の子)の行方を案じて、ここへきたのである。やがて源性は、全身焼けただれた幼児の死体を発見した。さらにくわしく調べると、わきの下あたりに菊の模様を染めぬいた小袖のしはが見える。「これこそ一幡様にちがいない」というので、その骨を高野山に運び、手厚くほうむったという。
※1202年(建仁2)親鸞30歳
玉日との間に範意(後の印信)が生まれる。
1207年(承元元年)親鸞35歳
2月建永の法難・・・法然は土佐(実際は讃岐)へ、親鸞は越後へ流罪となる。
4月九条兼実(玉日の父)没(59歳)。流罪をきっかけに愚禿親鸞と号する。
頼家の死
比企一族がほろんでから5日後、頼家は、母に命じられて出家した。さらに、そのすぐあとには、伊豆国(静岡県)修善寺へ送られた。先陣百騎、後陣二百騎の武士に守られ、侍女百人、輿三十という一行で伊豆へ進んだ行列は、まことに美しく、はれやかなものであつたという。しかし、山にかこまれた修善寺での頼家の暮らしは、さびしいものであった。
22歳という若さでありながら、ここにはその若さをぶつけて思いっきり行動できるような場所はない。ゆっくり話あえる親しい家来もいなかった。しかも、「せめて親しかった家来の何人かを、ここによこしてほしい」という頼朝の願いも、母の政子につめたく断られてしまった。こうして、頼家が修善寺へ来てから一年余りが過ぎたとき、「入浴していた頼家に、武士の一隊が襲いかかる」という事件がおこった。
このころにはすでに、北条時政の画策によって千幡(実朝)が第三代の将軍職についている。時政は、幽閉中の頼家が、将軍職への復帰をくわだてていることを疑い、刺客をさしむけたのである。頼家は、裸のままで、なんの武器を身につけていない。しかし、幼いときから武芸にすぐれ、勇武の士といわれた頼家は、むざむざと殺されはしなかった。すきをみて相手の武器をうばいとり、堂々と戦おうとした。しばらくはによみあいが続いたのだった。
そして、首に縄をかけ、手足をおさえつけて動けないようにしてうえでころしたのだと『愚管抄』は伝えている。頼家は、こうして死んだ。うまれながらの将軍であり、それなりの力を持ちながら、有力御家人の気持ちを察することができず、若くして一生を終えた悲劇の将軍であった。